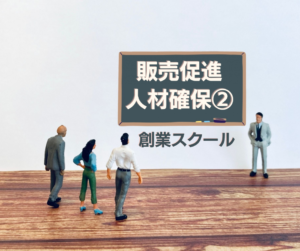熊本で中小企業診断士の資格をとるには? 熊本在住合格者からのアドバイス
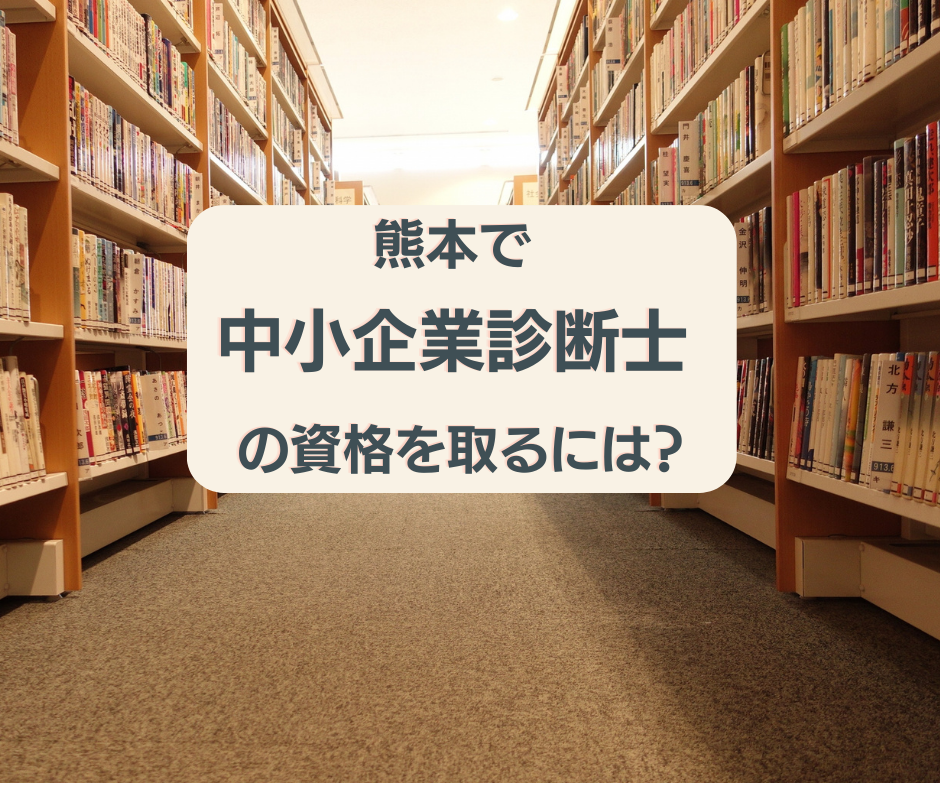
こんにちは。中小企業診断士の村田久(むらたひさし)です。
今回は、熊本で中小企業診断士の資格を取るには?について考えたいと思います。
この記事はこういった方にオススメ
- 中小企業診断士の資格に興味はあるけど、なかなか一歩が踏み出せない
- 熊本で中小企業診断士の資格の勉強をしたいけど、効果的な勉強法がわからない
- そもそも中小企業診断士って聞いたことはあるけど、よくわからない
熊本で中小企業診断士の資格を取るには
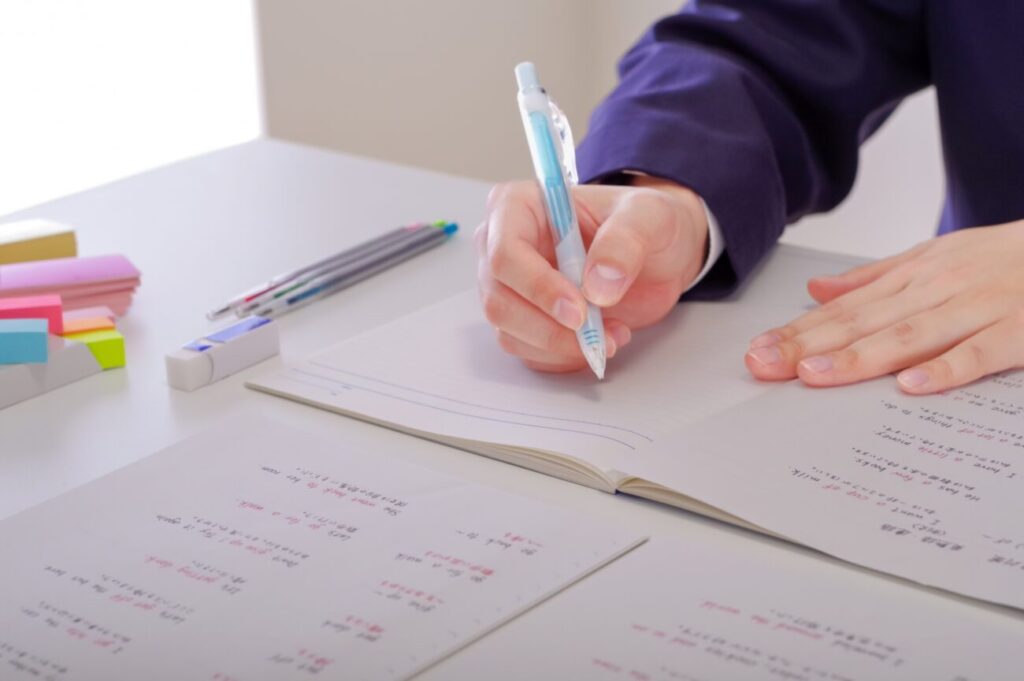
中小企業診断士の資格に興味を持たれたそこのあなた!
ようこそ!中小企業診断士受験「沼」へ!
中小企業診断士の試験は、やれば誰もが合格する内容であるにもかかわらず、人によって合格までの道のりがものすごく険しくなってしまう、非常に困難かつやりがいのある試験です。
特に筆記試験である2次試験は、正解が公表されないこともあり、本当に心が折れそうになる、非常に厳しい試験です。
それでも、中小企業診断士になりたい!という方、私が全力でサポートします!
まずは、熊本で中小企業診断士の資格を取りたい方向けに情報をまとめます。
熊本以外の地方で受験勉強をしようと思っている方は、勉強法の参考にしていただければ。
勉強の仕方やわからないことなど、お気軽にコメントやお問い合わせいただだければと思います。
いずれ、受験希望者が集まれば、勉強会なんかも開催したいな、と思っています。
中小企業診断士の勉強法は?
中小企業診断士試験は、1次試験7科目、2次試験4科目、口述試験と、3回にわたる試験を経た上で、合格となる、試験期間が長丁場の試験です。
正解がわからない2次試験はかなりの難関ですが、それよりもまずは一次試験7科目を突破する必要があります。
1次試験:経済学・経済政策、財務・会計、企業経営論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策
2次試験:組織人事・マーケティング・運営管理・財務会計
ざっくり、一次試験は1科目100点満点中60点以上、合計420点以上確保できれば、合格となります。
ただし、40点以下の科目が一つでもあると、足切りとなってしまい、420点を超えていても、不合格となります(科目ごとの合格制度もあります)。
まずは広い試験範囲を網羅的に学んだ上で、得意科目を伸ばし、不得意科目は50点くらいを確保できように底上げしていくのが無難な対応です。
また、試験範囲は変わらないのですが、経営情報システムや中小企業経営・中小企業政策は、毎年新しい情報が出題されるので、常にアップデートし続ける必要があります。
- 広い試験範囲への対応
- 毎年更新される科目への対策
- 正解のない2次試験をいかに乗り越えるか
こういった、中小企業診断士試験の特徴を考えるときに、まずオススメなのは「専門学校の講義」です。
一緒の目標に向けて頑張っている仲間がいると、お互いに切磋琢磨して、モチベーションを切らさずに勉強を行うことができると思います。
また、試験範囲が非常に広いので、自分では重要なポイントを絞るのが難しいのですが、経験豊富な講師がポイントを絞って説明してもらえるので、タイムパフォーマンスも良区なります。
それ以外には、「専門学校の通信講座(DVD視聴含む)」「参考書を見ながらの独学」などがあります。
専門学校の通学講座

熊本では残念ながら教室での通学講座はありません。
まあ、人口と受験生数から考えると、そんなに集まらないと考えられるので、仕方がないですね。
九州内で通学講座を行っているのは「TAC福岡校」ですね。
実は私も最初はTAC福岡講座に通っていました。
ただ、途中で転勤になってしまい、途中から通信講座に切り替えて勉強を続けました。
専門学校の通信講座

一番オススメな通学講座が、熊本では開講されていませんので、次の候補として、専門学校の通信講座が挙げられます。
通信講座というと、WEBで動画視聴する、というイメージがありますが、専門学校の校舎に行って、DVDの講座を視聴する「映像通学」というコースもあります。
この映像通学は、熊本では「資格の大原」で受講可能です。熊本駅近くで交通の便も良いところですね。
さらに、映像通学に参加できなかった場合も、WEBで視聴できるため、講義スケジュールを乱すことなく、勉強を進めることができます。
私は、転勤により通学ができずに、TACのWEB通信講座を受講しました。
結果として、一次試験はWEB通信講座で合格することができています。
自宅でもペースを乱すことなく勉強できる方は、WEB通信講座でも十分だと思います。
参考書を見ながらの独学
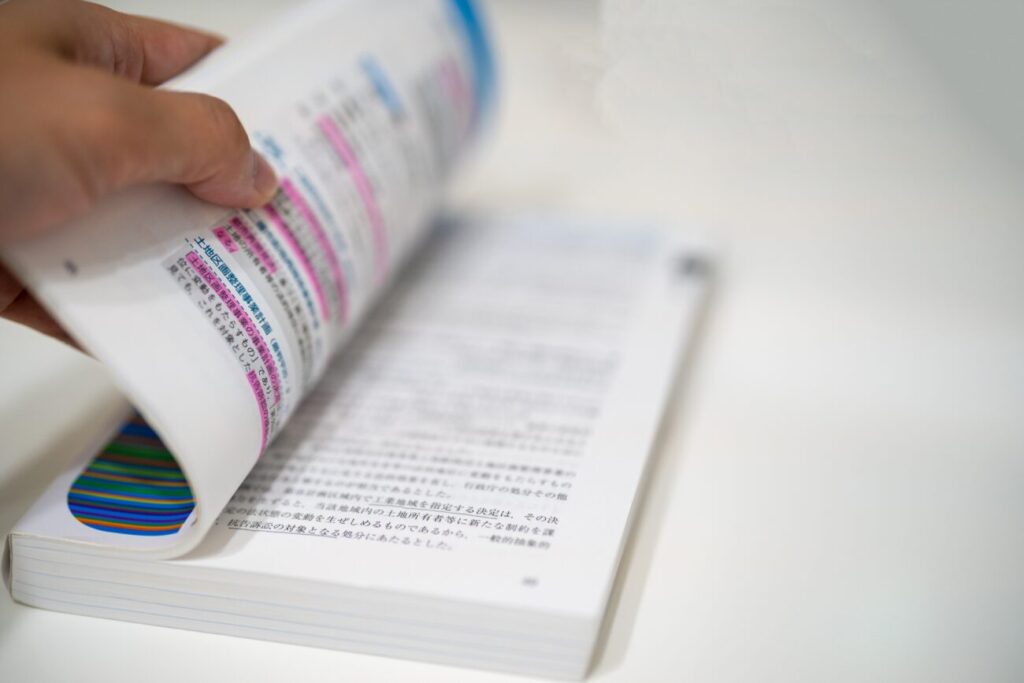
本屋さんにいくと、中小企業診断士試験に関する書籍が大量に並んでいます。
ただし、試験範囲が非常に広く、中には「財務・会計」「運営管理」「経済学」「法務」など、普段はあまり馴染みがない科目もあるため、テキストだけでは理解が十分にできない可能性もあります。
その場合は、各専門学校に「単科生」という制度がありますので、その不得意科目についてのみ、WEB通信講座を受講するという手段もあります。
1科目20,000円くらいから受講できますので、ポイントを絞って単科生の仕組みを使ってみるのはいかがでしょうか。
私も、2回目の一次試験を受験する際は、「経営情報システム」と「中小企業経営・中小企業政策」については、TAC単科生として受講し、無事に合格することができました。
中小企業診断士とは

ここまで読んでいただいた方は、もうご存知だと思いますが、中小企業診断士について、改めて説明します。
中小企業診断士(以下「診断士」という。)は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。
中小企業庁ホームページ
中小企業診断士制度は、「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」(以下「支援法」という。)第11条及び、「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年9月22日通商産業省令第192号)」に基づいて、経済産業大臣が登録する制度です。
要は、経済産業省が登録する国家資格であり、民間で活躍する経営コンサルタントです。
主に、中小企業の支援や公的機関でのアドバイザーなどを行うことが多いです。
ただし、資格を取得したからといって、独占業務があるわけでもなく、企業内に勤めながら取得している方も多く、取得しただけでほとんど活用できていない場合もあります。
活用していない方でも、5年ごとの更新は必要です。
更新に際しては、実際の診断実務が必要だったり、5回の研修受講が必要だったりと、なかなか取得後もハードルが高い資格です。
それでも、私は中小企業診断士の資格取得を強くオススメします!
中小企業診断士の資格取得がオススメの理由

中小企業診断士の資格がオススメな理由は、社会人として必要な知識が網羅的に身に付く、ということです。
例えば、一般的な会社員は、営業や製造などの技術や経験を得て成長していきますが、企業経営の根幹を支える「財務・会計」については、全く知識がない方がほとんどです。
「財務・会計」は専門的な社員がやるもの、と位置づけられている会社が大部分を占めていますが、逆に「財務・会計」の知識があれば、会社内で役に立つだけではなく、生活においても、住宅ローンを組むときや副業を行うときなどに、非常に役に立ちます。
他にも、一次試験の勉強をしている方とは、ビジネスの話をする際にも、基盤となるスキルが共通化されているため、無駄な説明が不要で、話が非常にスムーズに進みます。
社会人全員の必須科目にしたいくらいです。もしくは、学生の必須科目としても良いかもしれません。
それ以外にも、独占業務はないものの、独立して活躍している中小企業診断士もたくさんいるので、将来的なキャリアを描く際の選択肢が広がる、というメリットもあります。
そんな、中小企業診断士の資格、ぜひチャレンジしてみてください!
次回の記事では、初心者でもわかる!中小企業診断士の試験について、書かせていただきます。
中小企業診断士の村田久でした。